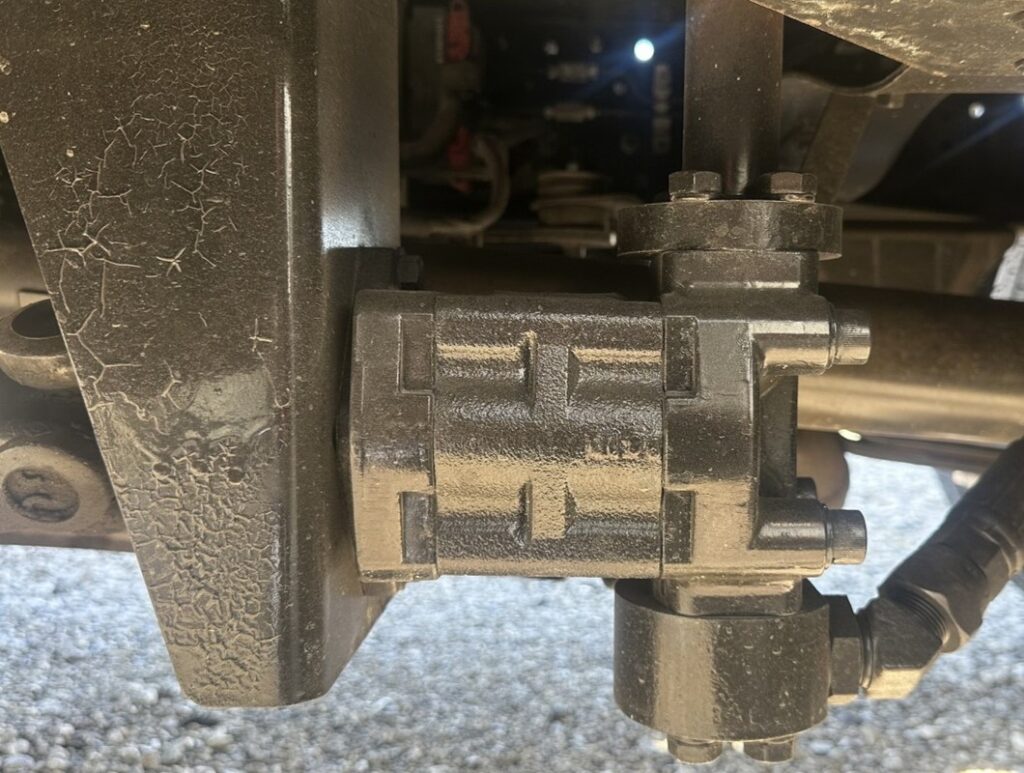昨年11月に仕入れた、トヨタ/ダイナ2tパッカー車。
只今、架装物(パッカー側)の整備に取り掛かっております。
年末、荷箱の錆を丁寧に落とし、シャーシブラック(防錆・保護)を全体に塗装しました。
年明け、いよいよ新品の押し出し板交換です。

中古パッカー車の仕上げは、一つ作業をするごとに調整が必要だったりします。
例えば今回、経年変化に伴い、荷箱の天井が新車時よりも少し下がっていたため、そのままでは押し出し板が入りませんでした。
一度戻して、押し出し板の上を慎重に削り、高さを合わせていきます。
再度、合わせてみましたが、もう少し調整が必要でした。

3度目、めでたくピッタリはまりました!
クレーンやフォークリフトを使って慎重に進めていく作業、無事に完了しホっとしました。
引き続き、お客様の安心安全を一番に、しっかりと点検・整備を進めて参ります!